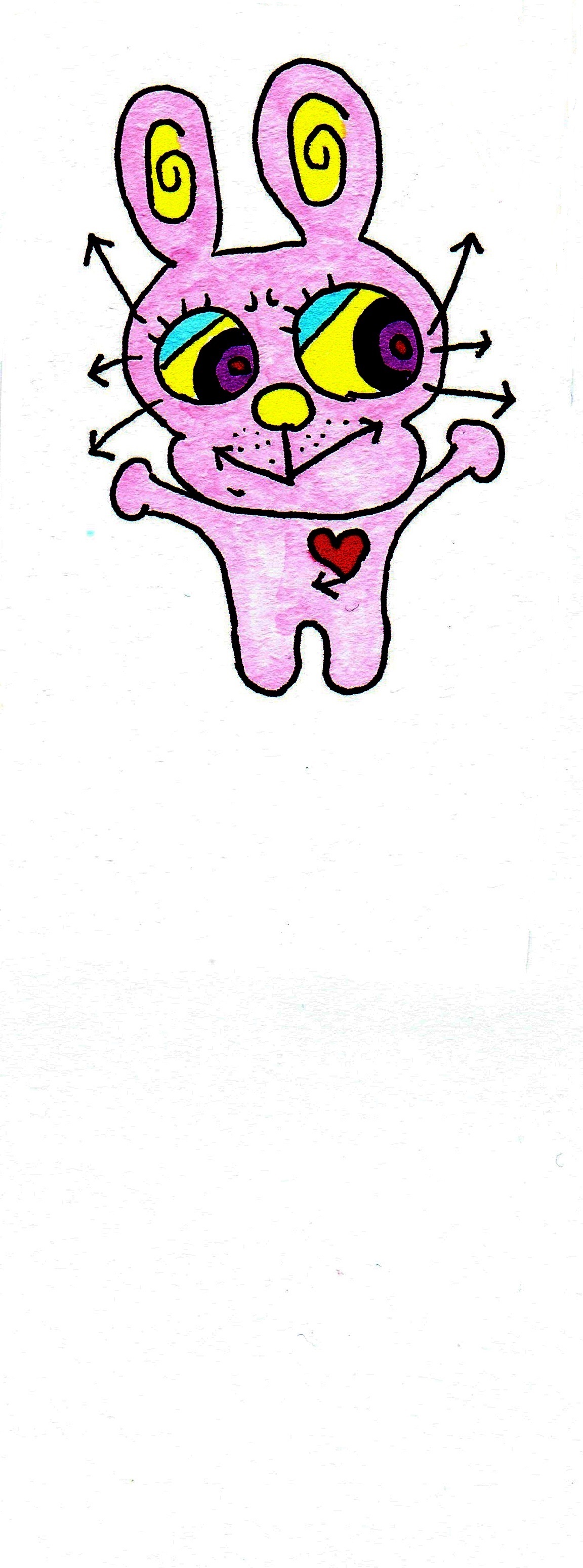教育漫才の発案者 「教育漫才で子どもたちが変わる」著者。
埼玉県越谷市立越ヶ谷小学校の田畑栄一校長先生。
漫才で子ども同士の人間関係を円滑にし、いじめや不登校をなくそうと取り組まれているそうです。
・田畑栄一の経歴
・いじめや不登校は減少方法は?
・人生の根っこを育てるって?
そこで今回は『田畑栄一の経歴は?いじめや不登校は減少方法は?人生の根っこを育てるも』と題しまして、お伝えしたいと思います。
それではさっそく、本題へ入っていきましょう!
田畑栄一の経歴は?
教育漫才の発案者 「教育漫才で子どもたちが変わる」著者、埼玉県越谷市立越ヶ谷小学校の田畑栄一校長先生。漫才で子ども同士の人間関係を円滑にし、いじめや不登校をなくそうと取り組まれています。これからどんなコラボができるか楽しみです。#教育漫才 #越ヶ谷小学校 pic.twitter.com/hQTDzzRJTV
— くまゆうこ ITでいじめのサインを見逃さない (@mamoru_yuko) October 6, 2019
・名前:田畑栄一(たはた えいいち)
・出身:秋田県大館市出身
・出身大学:早稲田大学第一文学部卒
・職業:越谷市立越ヶ谷小学校校長(2018年4月より)
教育漫才を試み、自殺ゼロ・不登校ゼロ・いじめ減少と学力アップの実績を残す。
経歴
田畑栄一校長の経歴なんですが・・・
田畑栄一校長は、早稲田大学第一文学部を卒業と同時に埼玉県公立中学校教諭(国語)として採用されたそうです。
埼玉県立越谷養護学校勤務後、岩槻市城南中学校教諭となりました。
その後中学校3校に勤務後、埼玉県教育局東部教育事務所に指導主事として勤務。
久喜市立久喜中学校教頭として管理職の道を歩み始め、2013年4月より5年間越谷市立東越谷小学校校長を経て、2018年4月より越谷市立越ヶ谷小学校校長として着任。
主な役職:
・東越谷小学校校長、埼玉県国語教育研究会副会長(2年間)
・埼玉県学校図書研究協議会副会長(3年間)
・共愛学園前橋国際大学COC評価委員(4年間)
・北海道教育委員会学力向上に関する総合実践事業道外アドバイザー(2年間)
・主な受賞歴、養護学校教諭時に日本肢体不自由教育研究発表会入選(一位)受賞
・中学校教諭時には埼玉県連合教育研究会論文(国語)入選(一位)
・埼玉教育論文(生徒指導)最優秀賞等数々の賞を受賞
・さらに指導主事時は埼玉県教育委員会主催施策提案で優秀賞(学力向上のための支援マップ)を受賞。
・H29には第66回読売教育賞優秀賞を受賞。
・埼玉県教育委員会優秀な教員(はつらつ先生)表彰を受賞らしいです。
田畑栄一校長は先生になるべきしてなったという感じですね・・・
いじめや不登校は減少方法は?
いじめは実際に起きています。
しかし、教育というのは理想、理念に向かって進まなくてはいけないと田畑栄一校長はいいます。
例えば:
校長が「いじめが多少あるのはしょうがないよね。」と言ってしまったら、
先生方も〝うちのクラスでいじめがあってもしょうがない〟と気がゆるみ、いじめを見逃してしまいます。
つまり校長や学校は〝いじめは絶対に許されないよ〟と断言しなくてはいけなく、
そして不登校の子はゼロにしようと努力しなくてはいけないのです。
〝学校は全員の子どもが揃ってこそ、初めて教育活動が始まる〟と
田畑栄一校長は言います。
不登校ゼロは可能?できる・できないではなく、それが理想であり、理想が叶うよう全力で取り組まなくてはなりません。
学校になじめない子どもに対して「学校に合わせなさい」というのではなく、「学校が合わせますよ」と言います。
みんなのための教育があると同時に、教育はひとりのためにもあるべきことだからです。
田畑栄一校長は、できることは何でもやってみる、その考えが、教育漫才というユニークな授業を生み出したようです。
新学習指導要領では、特に総合的な学習の時間で各学校のオリジナリティ、教科横断的な学び、地元に根ざした教育が求められています。
教育漫才は、クラスごとにくじ引きをしてペアを決めて、それからネタ作りをします。
くじ引きにすることによって、なるべく学級全体で、さまざまな子と交わるようにしているのです。
よく知らない子であっても、漫才のネタを作ろうとしたら、ふたりでたくさん話をしなくてはなりません。
話し合うことでわかり合うことができます。
それをみんなの前で発表する。
コミュニケーションやディスカッション、プレゼンテーションの力すべてが育まれるそうです。
さらに教育漫才で大事にしているのは、「死ね」「うざい」といった言葉を使わないこと、どついたり叩いたりしないこと、この2つのルールを守ることです。
そしてこれは、いじめにつながる大きな2つの要因でもあり、これを教育漫才を通して「いけないことだ」と体感し学んでくれたらと考え、先生方も指導しているそうです。
トゲのある教室をあったかい学級にする!
教育漫才をやった後とやる前では、人間関係がまるで違ってきたそうです。
教育漫才を通して、人をバカにしたり冷笑してはいけないこと、マイナスの笑いではなく、面白くて楽しくなるプラスの笑いに導くことで、学級の雰囲気は大きく変わったそうです。
学級の雰囲気が変われば、子ども達の様子も変わるということで、学級で友だちに悪い意味で「笑われる」ことがなくなれば、子ども達は積極的に手を挙げて発言するようになるそうです。
子どもは授業に集中し、結果的に学力の向上にもつながるそうです。
笑う門には福来たると言います。
田畑栄一校長はそれをもじって、〝笑う学校には福来たる〟と言っているそです。
逆になりますが、小さないじめが日常的にあり、学級が荒廃しているクラスを
田畑栄一校長〝トゲのある教室〟と呼んでいるそうです。
子どもや先生が持っている空気感、いじめに対する認識の欠如、トゲのある教室はいじめが生まれやすく、またクラスになじめない子が増え不登校につながるそです。
教育漫才でいじめは減ったそうですが、田畑栄一校長の努力もその中に沢山あると思います。
本当に子供が大好きなんでしょう。
そんな先生が沢山増える事を期待したいですね。
人生の根っこを育てる
人生の根っこを育てるを見通しの持てる管理職が求められると田畑栄一校長はいいます。
校長の役割は学校経営らしいです。
その学校がある地域の特性や実態をきちんと分析して、見通しを持って方向性を示し、決断することが必要で、教育委員会から降りてきたことをそのままやることも大切ですが、もっと良くなると思えばそれを教育委員会と相談し、交渉するのも校長の仕事の一つらしいです。
それが、子供が生き生きする学校につながっていきます。
学校現場においては、「最終責任は校長が取る」ということを明確にし、一人一人の教員が安心してやりたいことをやれる環境をつくることが大切らしいです。
田畑栄一校長もともと中学校の教師だったらしいのですが、2013年度に小学校の校長として初めて赴任したとき、何のために自分は中学校から小学校に行くのかを考えました。
そして、「人生の根っこ」づくりのためだったらしいです。
小学校は学力も大事ですが、いわゆる非認知能力、コミュニケーション力、目には見えないけれども人生を支えるような力、その人が醸し出すような資質を育てるべきだと思うそうで、算数や国語などは自分で努力すればできるようになるわけで、学校は数字で評価できない部分を育てていくことがとても重要です。
田畑栄一校長は、そのような「人生の根っこ」になる部分を育てたいと思っていらしゃるそうで、そこにずっとこだわってきたそうです。
Withコロナ時代にどんな教育活動が求められれているのでしょうか?
今のこの事態は、いわゆるペーパーテストで測れるような学力よりも、生きる力を学ぶときだと捉えています。
そのためには、知徳体のバランスが重要で、それが崩れてしまうといじめや不登校、うつなど、子供たちにもさまざまな弊害が出てきます。
コロナ禍で授業時間数を確保するために、技能教科の授業は通常の7割でよいとする現場への配慮がありました。
ありがたい半面、座学の教科を中心とした教育課程の在り方に、少し不安を感じます。
先の見えない時ほど、芸術や生活体験が心の糧になるからです。
座学ばかりだと子供も先生も苦しいわけです。
そこで学校独自の取り組みを始めた田畑栄一校長。
子どもが新担任と顔を合わす機会が始業式だけになることを案じていた。
「子どもが元気に過ごしているか確認する手段が必要だ。担任の教師と接する機会も作ってあげないと」
オンラインで「朝の会」ができないか。
早期実現は難しそうでしたが、何とか実現できたそうです。
なんでも気になる事はチャレンジする、これが田畑栄一校長です。
まとめ
今回は『田畑栄一の経歴は?いじめや不登校は減少方法は?人生の根っこを育てるも』と題しまして、お伝えしてきましたが、いかがでしたでしょうか?
ぶれることのない理想や理念を持ち、信じて歩んでいくこと。
「理念」などと言うと大げさに感じますが、私たち親もまた、試行錯誤しながらも、失敗を重ねながらも、「こうありたい」「こんな親になりたい」という理想に向かっていく姿をわが子に見せることこそが大切なのだと田畑栄一校長が教えてくださった様な気がしますね。
現在も「行動する校長先生」として、日々、教育現場の改善・改革に挑戦している。
そんな先生が増えたら、この社会も変わるような気がします。
今後の田畑栄一校長の活躍が楽しみです。
それでは、今回はここまでにさせて頂きます。
最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。